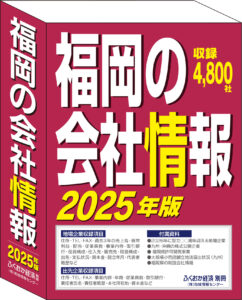NEWS
コロナ禍からのV字回復、3年で売上高1・5倍に 岩田産業グループホールディングス
Tag:
週刊経済2025年6月25日発行号
岩田会長インタビュー抜粋
㈱岩田産業グループホールディングス(福岡市博多区諸岡)の岩田陽男会長兼CEOは、本誌7月号「表紙の人」のインタビューに応え、躍進した直近の業績や新中期経営計画について話した。以下、インタビュー冒頭を抜粋。
―第7次中期経営計画の最終年度、2025年2月期連結決算の状況は。
岩田 連結売上高が、前期比9%増の約485億円、経常利益が2%増の増収増益で、いずれも過去最高だった。第7次中計初年度のKPIは売上高450億円に設定していたので、この目標を大きく上回る着地点となった。中計がスタートした時点の売上高が約310億円(2022年2月期)だったので、この3カ年で売上高はおよそ1・5倍に拡大、額にして175億円の増収になった。改めて、コロナ禍の苦境を社員が一丸となって乗り越えたからこそ、これほどのV字回復を達成できたのだと実感している。
―コロナ禍はまさに経営の危機だった。
岩田 2021年2月期の売上高は前期比30%減、金額にして約100億円の減収に見舞われ、営業利益も約15億円の赤字となるなど、過去最大の苦境に直面した。ただ、当社が苦しい時はそれ以上にお客さまも苦しい状況にあるはずなので、何としてもここは踏ん張らなければならないと、歯を食いしばって経営に向き合ってきた。特にこの時期は、㈱イワタダイナースが経営するピザ宅配専門店の「ピザクック」が内食や宅配需要の急増を受けて過去最高の売り上げを記録し、グループの苦境をカバーする役割を担ってくれた。
―では、直近の好調の要因は。
岩田 インバウンド効果による外食産業の活況に後押しされた。ここ2年ほどの外食需要の旺盛さは目覚ましく、往時を上回る勢いでインバウンドが福岡に訪れるようになり、少なからず外食需要を押し上げている。また社内的には、コロナ禍に取り組んだ事業の再構築や物流の見直し、生産性向上に向けた挑戦が、着実に実を結んできている。
一方で、主に原材料の高騰に伴う商品単価の値上げ局面が続いていることも、直近の業績には大きく影響している。ここ数年は原材料コストや人件費、物流費、エネルギーコストなど、ありとあらゆる分野で価格高騰の影響が著しく、一時は価格転嫁が追い付かず、逆ザヤ(仕入れ価格よりも売価の方が安くなっている状態)での販売を余儀なくされることもあったが、現在は価格転嫁もある程度円滑に進み、売り上げのボリュームを拡大する結果につながっている。
―「高騰」への対応は今後も大きな経営課題となる。
岩田 中でも物価の高騰、人件費の高騰が深刻で、これがメーカーなどに影響してさらなる商品単価の高騰が続く可能性も無視できない。生活者の節約志向が進んだ結果、外食控えにつながる懸念もある。各方面の状況をしっかり注視していかなければなりません。
―特にコメの価格急騰は深刻だ。
岩田 昨年に比べて3倍近くに高騰が進み、飲食店をはじめとするお客さまに大きな打撃を与えているのはもちろん、日本人の主食であるコメ需要の縮小、「コメ離れ」につながる懸念もある。当社としても、既存のお客さまへの供給を途切れさせないのが精一杯で、新規のお客さまは全てお断りせざるを得ない状況。これは実質的に顧客開拓の機会を失っていることになり、高騰で売り上げ規模こそ拡大しているものの、決して望ましい状態ではない。農林水産省は、今年度の作付面積が102%くらいと発表しているが、玄米価格で60㎏当たり3万円くらいまで落ち着くと、生産者は作りやすい、消費者は買いやすい環境になるのではないかと思うの。今後の農業政策に期待したいところ。